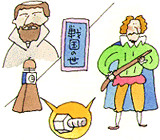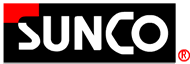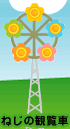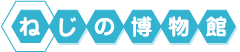
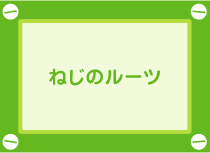
ねじのルーツは巻貝?
現在、さまざまなところで利用され、ねじがなければこれだけ機械文明が発達しなかっただろうといわれていますが、実はねじと人類の関わりは、本当偶然の出会いから始まったようです。浜辺で貝掘りをしていた原始人がたまたま先のとがった巻き貝を見つけて、それを葦の棒きれに突き刺し、回転してはずしたのが、ねじと人類の最初の関わりであったとされています。
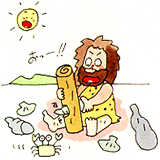
最初のねじはアルキメデス作?
ねじの形態をした最初のものは、アルキメデスの揚水ポンプであるといわれています。水を低いところから高いところに上げるためのもので、木製の心棒のまわりに木板を螺旋状に打ちつけたものが傾斜した木製の円筒の中に入っているものです。はじめは潅漑や船底にたまった水の汲み上げなどに使われていました。

レオナルド・ダビンチはネジフリーク?
ルネッサンス時代の天才・レオナルド・ダビンチが残したノートの中に、タップ・ダイスによるねじ加工の原理のスケッチが残っています。他にも、現在のねじのもとになるようなスケッチをたくさん残しています。主には締結用のねじですが、天才はやっぱり目の付け所がーーー。 ザビエルが伝えたネジ
日本に伝わったのは、1549年に来日したフランシスコ・ザビエルではないかといわれています。領内でのキリスト教の布教活動を許してもらうために、大内義隆に自鳴機(機械時計)を贈りました。どうやら、その中に使用されていたねじが我が国へのねじの伝来のようです。また、1543年に種子島に漂着したポルトガル人の持っていた火縄銃の底栓が、日本人が見た最初のねじであるとされています。