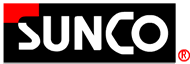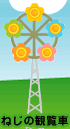![]()
【ISO】 アイエスオー
International
Standard
Organization の略
Standard
Organization の略
【ISOマーク】 アイエスオーマーク
JIS小ねじと区別する為に、ISO小ねじの M3,M4,M5の頭部についている丸いくぼみ。JIS規格が変更になった際、頭部形状に変更はなく、M3,M4,M5のピッチのみ変更になりました。そこで、このサイズのみ区別する必要が生じ、新しいJIS規格の物の頭部にくぼみを付けることが慣例となりました。(M3,M4,M5以外はマークなし)
新しいJIS規格はISO(国際標準化機構)の規格に準じて制定されたので、このくぼみはISOマークと呼ばれるようになりました。
※’96年に小ねじのJIS規格はさらに改定された為、いわゆるISOは旧JIS、いわゆるJISは旧々JISというのが正しいということになります。
新しいJIS規格はISO(国際標準化機構)の規格に準じて制定されたので、このくぼみはISOマークと呼ばれるようになりました。
※’96年に小ねじのJIS規格はさらに改定された為、いわゆるISOは旧JIS、いわゆるJISは旧々JISというのが正しいということになります。
【アイボルト】 アイボルト
丸い穴があるリング状の頭をしたボルト。中でも頭の付け根に座を付けたものは、主としてつり上げ用として用いられ、この種のものを”つりボルト”(lifting eyebolt)ということがある。(同じくボルトの変わりに環が付いたナットをアイナットと言う)
【亜鉛】 アエン
元素記号:Zn 原子番号:30 原子量:65.41
金属元素の一つで青白色を呈し、水に溶けず、酸、高温アルカリに溶ける。
最も重要な用途は鉄鋼の防食で、浸漬メッキのほか、鋼構造物の犠牲電極に使われている
。亜鉛に対する規制として日本ではPRTRの第一種対象物質に指定されている。
金属元素の一つで青白色を呈し、水に溶けず、酸、高温アルカリに溶ける。
最も重要な用途は鉄鋼の防食で、浸漬メッキのほか、鋼構造物の犠牲電極に使われている
。亜鉛に対する規制として日本ではPRTRの第一種対象物質に指定されている。
【亜鉛黒】 アエングロ
黒色クロメートの事
【亜鉛めっき】 アエンメッキ
代表的な防錆処理として主に鉄素地の錆止めに広く用いられる。亜鉛めっき単体では酸化されやすい(錆びやすい)ので、めっき後その上ににクロメート処理(化成被膜処理)を施し、これにより亜鉛表面の耐食性が増し、外観の美しさが備わります。
【アプセットボルト】 アプセットボルト
ボルト頭を圧造によって六角、四角などに成形したボルトの事。
冷間圧造による六角頭のアプセットボルトは、頭部上面にへこみがあるのが普通である。
市場には4マーク、7マーク、十字穴付き、セムスなどの形状が見られる。
冷間圧造による六角頭のアプセットボルトは、頭部上面にへこみがあるのが普通である。
市場には4マーク、7マーク、十字穴付き、セムスなどの形状が見られる。
【アメリカねじ】 アメリカネジ
1864年にアメリカ人ウィリアム・セラーズがウィットねじに改良を加え、山の角度60°のインチ系ねじを学会に発表、セラーズねじとして広まり1868年にアメリカの政府関係事業に全面的に採用され、セラーズねじ、あるいはアメリカねじとして知られるものとなる。なおこれは第2次大戦中に武器などのねじの互換性の必要から、アメリカ・イギリス・カナダの三国が協定してつくったユニファイねじに発展する。
【あら先】 アラサキ
ネジ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの。小ねじ類はあら先が標準である。
【アルマイト処理】 アルマイト
アルミニウムに対して行う処理の一つで、別名アノダイズ処理、アルミニウム陽極酸化処理ともいう。
まず電解液中でアルミニウムを陽極として電気分解し、その表面に陽極化酸化被膜を生成させて防蝕、耐磨耗性を向上させ、装飾的にも利用される事がある。
まず電解液中でアルミニウムを陽極として電気分解し、その表面に陽極化酸化被膜を生成させて防蝕、耐磨耗性を向上させ、装飾的にも利用される事がある。
【アルミニウム】 アルミニウム
原子番号13、元素記号 Al 1円玉の原料として有名。熱と電気を良く通す銀白色の軟らかい軽金属。
鉄に比べて約1/3ほどの比重で軽量という特徴がある一方、純アルミニウムは軟らかい金属である為、銅、マンガン、ケイ素、マグネシウム、亜鉛、ニッケルなどと合金にすることで強度のある金属材料として応用される。ビス類では一般的に、ボルト・小ねじ・リベットでは5000系、六角穴付きボルト(キャップスクリュー)では7000系、ナットでは5000系や2000系、ワッシャーでは1000系が主に利用される。
鉄に比べて約1/3ほどの比重で軽量という特徴がある一方、純アルミニウムは軟らかい金属である為、銅、マンガン、ケイ素、マグネシウム、亜鉛、ニッケルなどと合金にすることで強度のある金属材料として応用される。ビス類では一般的に、ボルト・小ねじ・リベットでは5000系、六角穴付きボルト(キャップスクリュー)では7000系、ナットでは5000系や2000系、ワッシャーでは1000系が主に利用される。
【アンカー】 アンカー
構造物をコンクリートの基礎と結びつける役目をするボルトをアンカーボルト(anchor bolt)と呼び,これがアンカーの語源と言われる。現在では構造物にしっかりと固定する金物や接着材をアンカーといい、コンクリート等にあと付けする固着機能を有するものをあと施工アンカーという。