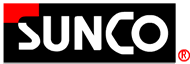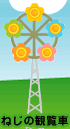![]()
【メッキの語源】 メッキノゴゲン
「メッキ」とは、カタカナで表すことが多く、外来語のように思えますが、これは日本語です。「めっき」とした方が正しい表現なのでしょう。
英語では、PLATING(プレイティング)となります。
昔は、水銀に金を溶け込ませたもの(アマルガム)を被メッキ体に塗りつけそれを加熱し水銀のみを蒸発させて金を付着させる方法を用いたようです
奈良の大仏などはこの方法でメッキされています。
この方法を滅金(めっきん)と呼び、いつか「ん」がとれて「めっき」と呼ばれるようになったともいわれています。
なお現在では「鍍金」という字を当てて「メッキ」と読ませています。
英語では、PLATING(プレイティング)となります。
昔は、水銀に金を溶け込ませたもの(アマルガム)を被メッキ体に塗りつけそれを加熱し水銀のみを蒸発させて金を付着させる方法を用いたようです
奈良の大仏などはこの方法でメッキされています。
この方法を滅金(めっきん)と呼び、いつか「ん」がとれて「めっき」と呼ばれるようになったともいわれています。
なお現在では「鍍金」という字を当てて「メッキ」と読ませています。
【メッキ不良(クローム・ゲージ)】 メッキフリョウ(クローム・ゲージ)
クローム鍍金を施したネジはGRⅠ(1級通り)ゲージに通りません。
<その理由は>
1.下地のニッケルメッキの厚みが薄すぎると光沢がなくなる為、メッキ厚を5μ以上
(最大13μ)で設定している。
2.クロームメッキは着き廻りが悪い為、1回のメッキでは綺麗に着かず、着きの悪い物を選別し、
もう一度着け直すことを行っています。(着けなおした物はさらに1μ程厚くなります)
*上記1.2.を行えばゲージに通らないことが多くなるが、これをおろそかにすれば美観が悪いものが多発し装飾性が失われます。
したがってクロームメッキに関してはナットに通れば良品と見なしています。
<その理由は>
1.下地のニッケルメッキの厚みが薄すぎると光沢がなくなる為、メッキ厚を5μ以上
(最大13μ)で設定している。
2.クロームメッキは着き廻りが悪い為、1回のメッキでは綺麗に着かず、着きの悪い物を選別し、
もう一度着け直すことを行っています。(着けなおした物はさらに1μ程厚くなります)
*上記1.2.を行えばゲージに通らないことが多くなるが、これをおろそかにすれば美観が悪いものが多発し装飾性が失われます。
したがってクロームメッキに関してはナットに通れば良品と見なしています。
【メッキ不良(クロームくもり)】 メッキフリョウ(クロームクモリ)
クロームメッキは着き廻りが悪いため、1回のメッキ作業ではメッキが綺麗に着かず、着きの悪い物を選別し、もう一度、着け直すことを行っています。
この着きの悪い物を選別する作業は、目視で行っている為、見逃したり、作業する人の基準が甘いと、美観の良くない物が混入する場合があります。
この着きの悪い物を選別する作業は、目視で行っている為、見逃したり、作業する人の基準が甘いと、美観の良くない物が混入する場合があります。
【メッキ不良(十字穴に錆?)】 メッキフリョウ(ジュウジアナニサビ)
実際には錆びているわけではないのに十字穴が錆びていると言われることがあります。
1.銅下ニッケル、銅下ニッケルクロームで下地の銅が見えている場合。
まだ錆びているわけではありませんが、ニッケルおよびクロームののりが悪いので耐食性は
劣ります。(元々ニッケルやクロームはそれほど良くはない)
2.グリーンクロメートで茶色のシミが着く。十字穴にメッキ液がたくさん残ったまま乾燥し、
クロメート被膜が厚く着いた状態。
逆に耐食性は良くなっているのですが、見た目で錆びていると言われることがあります。
1.銅下ニッケル、銅下ニッケルクロームで下地の銅が見えている場合。
まだ錆びているわけではありませんが、ニッケルおよびクロームののりが悪いので耐食性は
劣ります。(元々ニッケルやクロームはそれほど良くはない)
2.グリーンクロメートで茶色のシミが着く。十字穴にメッキ液がたくさん残ったまま乾燥し、
クロメート被膜が厚く着いた状態。
逆に耐食性は良くなっているのですが、見た目で錆びていると言われることがあります。
【目付】 メツケ
単重。製品1ヶの重さ。
鉄と比べた同じ大きさの他の金属の目付は
鉄と比べた同じ大きさの他の金属の目付は
| 黄銅 | =鉄X1.08 | となります。 |
| ステン | =鉄X1.01 | |
| チタン | =鉄X0.57 | |
| アルミ | =鉄X0.35 |
【面取り】 メントリ
角が立たないように削ること。一般的にはC面は45度゜で取る。
【面取り先】 メントリサキ
ねじ部先端面が切断のままで、端部の角をほぼねじの谷の径まで面を取ったもの。
【面取り部 chamfer】 メントリブ
雄ねじと雌ねじが食い付きやすくなるように、ネジ部の端に設けた面取りの部分。