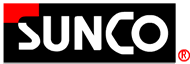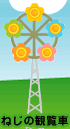![]()
【水素脆性】 スイソゼイセイ
水素脆性とは、メッキしたネジの頭が、相手に締め付けたとたん、またはしばらくして頭がとれてしまう現象である。
ネジをメッキするときは、前工程として酸洗いをする。酸洗いとは、ネジをカゴに入れて硫酸または塩酸水溶液中に保持して鉄表面の錆を溶かして除去する作業である。
このとき、酸と鉄とが化合して発生する水素の一部が鉄中に入り込んで鉄の粒子の境界にたまり、ついにその境界から粒子を押し広げて、もろいものにしてしまう現象である。
※熱処理しないボルトではメッキしても水素脆性の心配はない。
ネジをメッキするときは、前工程として酸洗いをする。酸洗いとは、ネジをカゴに入れて硫酸または塩酸水溶液中に保持して鉄表面の錆を溶かして除去する作業である。
このとき、酸と鉄とが化合して発生する水素の一部が鉄中に入り込んで鉄の粒子の境界にたまり、ついにその境界から粒子を押し広げて、もろいものにしてしまう現象である。
※熱処理しないボルトではメッキしても水素脆性の心配はない。
【スキミゲージ】 スキミゲージ
隙間を測るゲージ
【すずコバルトメッキ】 スズコバルトメッキ
すずとコバルトの合金被膜。クロームメッキの色合いに近く代用として利用される。
クロームに比べつきまわりが良く安価でバラツキが少ないが、耐食性は劣る。
クロームに比べつきまわりが良く安価でバラツキが少ないが、耐食性は劣る。
【スタック】 スタック
止め輪などの製品で、作業性を考慮して工具に喰いつきやすいように棒状に整列させ、テープなどで貼り付けた梱包のこと。
【ステンコート】 ステンコート
ジンロイ+Kコート
亜鉛ーニッケル合金メッキのジンロイの下地に光沢クロメート処理をし、その上に無色透明の防錆コーティング剤のKコートを施します。
見た目も耐食性もステンレスのようになることから「ステンコート」と呼ばれている。
ステンレスの焼き付け防止用コートと混同されやすいので注意が必要。
亜鉛ーニッケル合金メッキのジンロイの下地に光沢クロメート処理をし、その上に無色透明の防錆コーティング剤のKコートを施します。
見た目も耐食性もステンレスのようになることから「ステンコート」と呼ばれている。
ステンレスの焼き付け防止用コートと混同されやすいので注意が必要。
【ステンレス】 ステンレス
Fe(鉄)を主成分(50%以上)として、10.5%以上のCr(クローム)を含む合金鋼
マルテンサイト系
SUS410=Cr13%+Fe87%
フェライト系
SUS430=Cr18%+Fe82%
オーステナイト系
SUS304=Cr18%+Ni8%
SUSXM7=Cr18%+Ni9%+Cu3%
Crが鉄よりも酸素と結びつきやすいため、鉄より先にCrが酸化し、表面に酸化Crの膜を作るため(不働態化)ステンレスは錆びにくい。
マルテンサイト系
SUS410=Cr13%+Fe87%
フェライト系
SUS430=Cr18%+Fe82%
オーステナイト系
SUS304=Cr18%+Ni8%
SUSXM7=Cr18%+Ni9%+Cu3%
Crが鉄よりも酸素と結びつきやすいため、鉄より先にCrが酸化し、表面に酸化Crの膜を作るため(不働態化)ステンレスは錆びにくい。
【ステンレスの旧記号】 ステンレスノキュウキゴウ
旧 SUS24 ⇒ 新 SUS430
旧 SUS27 ⇒ 新 SUS304(SUS305J1、SUSXM7)
旧 SUS27 ⇒ 新 SUS304(SUS305J1、SUSXM7)
【ストロンジンク】 ストロンジンク
亜鉛ー鉄合金メッキで、塩水噴霧試験で白錆500Hr、赤錆2000Hrの超高耐食性です。
銀を使わない黒色クロメート処理が簡単にできます。
合金比は凹部凸部も均一で、耐食性が安定しています。
銀を使わない黒色クロメート処理が簡単にできます。
合金比は凹部凸部も均一で、耐食性が安定しています。
【スラスト方向】 スラストホウコウ
止め輪などを挿入する際に使用される言葉で、
軸部に対して、180度の方向を「スラスト方向」という。
90度の方向を「ラジアル方向」という。
軸部に対して、180度の方向を「スラスト方向」という。
90度の方向を「ラジアル方向」という。
【スリワリ】 スリワリ
筋割ともいう。ねじ回しの先端を差し込んで、ねじ部分を回転するために設けたマイナス溝。